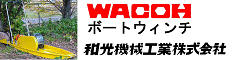岩波新書、1992年10月刊 著者は、京都大学医学部卒で、各地の病院に勤務し、第一線の外科医として活躍しています。その傍ら、高山路爛のペンネームで小説、エッセイを発表し、「虫垂炎—100年の変遷・その臨床と病理」(へるす出版)、「私の名診・誤診・速診」(旺史社)、「王国への道—古代アステカ滅亡史」(旺史社)、医学マンガ「メスよ輝け!」の連載など、多数の著書があります。
世間一般に言われる「盲腸」とは、解剖学的には「虫垂突起」が正しく、大腸の起始部である「盲腸」の先端からチョロンと飛び出た小器官です。日本の医療は、この小さな「虫垂」から、本格的に始まりました。今ではとても考えられませんが、明治の黎明期には天下の帝国大学医学部付属病院の外科病棟では、大半がこの炎症の患者で占められていたのです。日本外科学会報告に堂々と「盲腸炎および虫様突起炎」というタイトルがあり、その「盲腸炎」が一人歩きしてしまいました。誤りが正されたのは、昭和20年代になってからのことです。
問題はその「虫垂炎」(アッペ)がやたらに切除されてきたことでした。日本人のおよそ5人に一人、欧米先進国の2倍です。しかし近年、「虫垂」はリンパ組織の宝庫であることが明らかになり、「虫垂」の切除は免疫力の低下を招くと指摘されることになりました。
よく「外科はアッペに始まり、アッペに終わる」といわれます。確かに「たかがモーチョー」ですが、実はアッペの診断は奥が深いのです。どんな名医でも誤診は避けられません。本書では、これまで著者の関わった様々な事例が紹介されていますが、その赤裸々な実態は驚くばかりでした。基本的には切らずに「散らす」ことですが、どうしても「開く」しかないときに、それが意外な展開になることがあるのです。アッペが破れて腹腔内全体にウミが散らばった「汎発性腹膜炎」で、現在消化管穿孔後生命が保証できるのは48時間ほどで、ゴールデンタイムと呼ばれ、抗生物質で徹底的に洗うことで乗り切れますが、「遺残膿瘍」があると重篤な合併症を招いて大事になります。誤診で苦労したのは、十二指腸潰瘍の穿孔や肝臓破裂による出血で、さらに脾臓破裂の事例までありました。女性の場合は、婦人科の領域になることも多々あります。アッペの鑑別診断には、常に慎重を要するのです。
著者の外科医の経歴は25年にも及び、第一線病院での手術は優に5千件を超えますが、それでもなお未経験の疾患は数えきれません。誤診や合併症は苦しいものですが、より多くの辛い経験を積んだ医者こそが大成するのです。著者はこれまで多くの医者を見てきましたが、アッペの鑑別診断をきちんとやれる医者は皆無でした。大学病院などでは、どうしても経験が限られます。今日では、超音波やCTなどが普及していますが、それでも100%確認できるわけではありません。“広く、浅く”ではなく、“広く、深く”でなければ、優れた外科医とは言えないのです。麻酔の技術も、大きなカギを握っています。名医中山恒明氏は、かって「どんな医者に出会うかで寿命が決まる」と述べました。まさに至言でしょう。著者はそれに加えて、一人の外科医が、どんな上司とめぐり会うかで今後の成長が決まるとして。敬服する3人の名医を挙げ、そのすべてを学ぶことを心がけています。近年はもっぱら「ガン」が注目されていますが、アッペの診断と手術にこそ、外科医の真髄があるのです。「了」