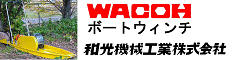角川選書、平成30年12月刊 著者は、熊本大学法文学部史学科卒で、現在は熊本大学大学院人文社会科学の教授です。主な著書に「タネを播く縄文人、最新科学が覆す農耕の起源」(吉川弘文館)があり、第5回古代歴史文化賞大賞を受けています。昆虫の専門家ではありませんが、縄文土器を発掘すると、その中に多くの昆虫が練り込まれ、また圧痕として残されていたことから、あらためて「昆虫考古学」を立ち上げました。虫たちが、古代人の暮らしを語っていたのです。
昆虫の種類は、現在100万種以上が知られており、日本だけでも33000種が棲んでいます。彼らが出現したのは約4億年前で、ヒトよりはるかに古い時代から栄えていました。その生態は、ごく小規模な住環境を反映し、変温動物なので特に気温に敏感です。気候や環境の変化があると、遺伝的な適応よりも場所を移動して食物選択を広げ、適応してきました。昆虫は、すくなくても数百万年の間は、形態的、生態的、生理的にほとんど変化していません。そのため同定がしやすく、環境史の復元に、極めて有効な指標となるのです。
野生植物の栽培が始まると、植物は遺伝的形質を変えながら、人間にとって有用な形質に変化してゆきました。一方それらの植物を食べていた昆虫は、自分の形を変えずに好みの場所を探して移動しました。人間の貯蔵した穀物は、その最高の場所だったのです。コクゾウムシの仲間がその代表でした。「貯蔵食物害虫」の誕生です。それも穀類や豆類などを直接食害するコクゾウムシ類などの「一次性害虫」と、それらを粉などに破砕したものを好むノコギリヒラタムシなどの「二次性害虫」、さらに湿気で傷んだものや菌を食べるゴミムシダマシ類などの「周辺害虫」に分けられます。また家屋に浸入するハチ、アリや、ゴキブリなども「家屋害虫」とされました。しかし彼らは、環境が変わるとまた野生にも戻りました。
人が定住化し、農耕や牧畜を始めると、穀物や食料を貯蔵するようになり、人と害虫が密接な関係を持つようになりました。考古学の分野でも注目はされましたが、その出土状況はさまざまで、英国のローマの遺跡からは、大量の貯蔵食害虫の遺体が発見されています。
日本でも、三内丸山遺跡から多量のコクゾウムシの遺体が見つかり、これは食害された堅果類と一緒に廃棄されたようです。生息域の広いコクゾウムシが、ここまで来ていたのです。また土器の圧痕は多く、材木を食べるオオナガシンクイ、糞を食べるマグソコガネ、ドングリやクリを食べるクリシキゾウムシや、キクイムシの仲間などで25種もいました。遺跡の土壌では、自然昆虫も入りますが、土器の圧痕なら屋内害虫だけの実態がつかめます。著者の調査では、コクゾウムシが87%を占め、人間と共存したダントツの家屋害虫でした。
土器圧痕は家屋害虫学の大きな手がかりを与えてくれます。体全体はもちろん、幼虫でも表面や柔らかい組織もよく保存されており、X線を使えば土器内部からも検出できます。
縄文人は昆虫を食べていたでしょうか。東南アジアなどでは、現在も一般的ですが、縄文遺跡の糞石からはまだムシの遺体は発見されていません。状況証拠があるのに意外でした。
さらに昆虫遺体は、床下、ゴミ箱、トイレ、下水道からもたくさん見つかります。エジプト・ファラオの墓にもいたそうです。先史・古代の昆虫採集が、今も続いています。「了」