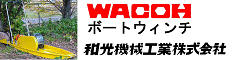新潮選書、2019年1月刊 著者は、東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了した、分子古生物学の専門家です。これまでに「化石の分子生物学」、「宇宙からいかにヒトは生まれたか」、「爆発的進化論」、「絶滅の人類史—なぜ私たちは生き延びたのか」など、一般向けに多くの著書があります。
進化学という分野は、ダーウィンの進化論がもっともよく知られていますが、早くから誤解されたり、とんでもない説が生まれたりして、さまざまな論争が現在まで続いています。
ダーウィンの「種の起源」では、科学書として①多くの証拠を挙げて、生物が進化することを示し、②進化のメカニズムとして自然選択を提唱し、③進化のプロセスとして、分岐進化を提唱しました。生物が進化すると考えた人は、それまでにもたくさんいましたが、「仮説」を「検証」したことで、「種の起源」が不滅の名著となったのです。しかし「種の起源」は神学書でもありました。初版では、自然選択などの進化の法則を、神の設定としたのです。そのためキリスト教会で支持する人も出ましたが、ダーウィン自身は次第に神と距離を置くようになります。変異はランダムに起こり、その中で生存力や繁殖力を高めたものが残ったとしました。「進化」には「進歩」の意味はなかった。それは現在の進化生物学でも同じです。ところが、グレイやスペンサー、ラマルクなどが、「進化」を「エボリューション」として「進歩的進化論」を世に広め、その誤解が今日まで人々に伝わってしまいました。
「種の起源」には、今からみると誤りもたくさんあります。まず自然選択の漸進的変異説は、当初から人気がありませんでした。突然変異説が浮上したからです。メンデルによる遺伝の法則も、連続的な変異には合いません。変異は次第に薄まってゆきそうです。しかし、1908年にハーデイ・ヴァインベルグは、対立遺伝子と遺伝子型の組み合わせから、変異は世代を超えても薄まらないこと、集団が小さいと男女比率が偏るような遺伝的浮動が起きることを発見しました。生物には安定化への選択と、方向性の選択があり、形態が殆ど変化しない時期と、急速に変化する時期を繰り返す、断続的進化をしていたのです。ここに進化のメカニズムが隠されていました。またケネス・マザーは1943年に、一つの形質に多くの遺伝子が関係すれば、連続的変異があるという「ポリジーン説」を唱え、自然選択説を蘇らせました。環境要因による獲得形質が遺伝する、エピジェネテイクスも確認されました。
国立遺伝研究所の木村資生は、遺伝的浮動に注目して、1968年に「自然選択による進化よりも、偶然による遺伝的浮動の進化のほうが多いという中立説」を主張しました。進化速度や、多くの現象にうまく適合します。変異は必然で、そこに「偶然」が関与するのです。
また今西錦司は、自然選択を全否定して定向進化説をとり、「競争原理」に対して「共存の原理」を挙げましたが多くのムリがあり、科学より思想とみたほうが良さそうです。
本書ではさらに、「生物の歩んできた道」を振り返っています。単細胞生物は、永遠に分裂して死なず、多細胞生物は、生殖細胞を残して体細胞を使い捨て、死ぬ運命となりました。肺も四肢も、すでに水中で進化していたこと、恐竜と鳥の関係、車輪を持つ動物がなぜいないのか。なぜヒトだけが直立2足歩行に進化したのか。それぞれに説得力がありました。了