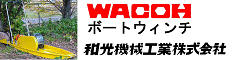吉川弘文館、2013年10月刊 著者(1901~1987年)は、第八高等学校を経て東京帝国大学文学部国史学科を卒業、母校で助教授、1945年に教授となりました。この間、戦前から戦後への日本史研究の激動の重責をほぼ一人で担い、戦後の日本史研究の基礎を築きました。1953年から11年にわたり東京大学史料編纂所の所長を兼務、1982年には文化勲章を受章しています。
本書は、1980年から2年間にわたり雑誌「歴史と人物」に連載された学術エッセイで、「日本書紀」から「日本開化小史」までの29冊の史書を取り上げ、正規の六国史や物語文学などの史料的性格を一貫した視点で論じて、史書を読む楽しさを縦横に語っています。
「日本書紀」は一般にとりつき難い本だと思われていますが、実はとても面白い。例を挙げれば「崇神紀」にある「箸墓」の起源は、なんとも艶めいた物語ですし、終わりに近い「天武・持統紀」にも、壬申の乱における瀬田川の攻防など、まるで講談のような軍記物語が記されています。学問的に見ても不思議です。勅撰の史書でありながら前後に矛盾があり、用語も不統一です。改新の詔でも、編者の時代の制度を、昔にあったように述べて大きな批判を浴びました。しかしすべてが怪しいとも言い切れない。地方行政機関の国-郡-里に、評や郷の呼び名を使うか、時代を確認する論争が続いて、著者にはこだわりがありました。
「続日本紀」は六国史の2番目で、文武天皇から桓武天皇までの94年間を対象にして、奈良時代をほとんどカバーしています。しかし史書としては出来が悪い。編者が前後で変わったことに加え、桓武天皇は自分の治世まで記述させたたことで、長岡京遷都に際しての皇太子廃位事件の祟りを怖れ、関連記事を削除させました。現代史は、常に恐ろしいのです。
「日本後紀・続日本後紀」、さらに「文徳実録」、「三代実録」へと180年間、一年の断絶もなく国家の修史事業が続きました。これは律令国家の文化水準の高さを示しています。
著者は、ここであらためて「古事記」を取り上げました。民族的叙事詩などとも評されますが、「古事記」も勅撰の史書です。正史を補完する役割は、認めて当然でしょう。序文によれば、当時残されていた「帝紀」と「旧辞」のみによって書かれています。一方、その8年後に出た「書紀」は、それ以外の史料も使っていました。両書の違いはそれだけなのです。
帝紀とは、神代から推古天皇までの歴代の系譜です。旧辞は神々の物語、天皇や英雄、男女の逸事などの情緒豊かな物語で、継体天皇の頃までが伝えられていました。著者は「記紀」において、もとになった帝紀に大きな差がなかったことに注目しました。天皇の名だけでなく、后妃、宮都、山稜の名も同じなのです。本来の帝紀がよほど確立していたのでしょう。天武天皇崩後の書紀に、恣意的な修正はありませんでした。戦後の天皇の系譜を疑う説に対して、「記紀」で一致する「帝紀」の重みを感じます。皇位継承についての、永野祐氏の新説では皇統が三つあって、古王朝(呪教王朝)、中王朝(征服王朝)、新王朝(統一王朝)としました。根拠は、古事記にある天皇の崩年が、崇神天皇以下の15代だけ明記されていることでした。実在はこれらの天皇だけというのです。しかしこれには不自然な点が多い。著者は、それだけでは帝紀を疑えない、今後の重要な研究課題であると述べています。「了」