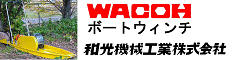カール・ジンマー著、斎藤隆央訳、白揚社2023年7月刊
著者は、アメリカを代表するサイエンス・ライターです。ニューヨーク・タイムズなどで多くの賞を受けています。イエール大学分子生物物理学・生化学科の客員教授。小惑星などに名を遺し、著書には「カラー図解 進化の教科書」(共著、講談社)、「進化・生命のたどる道」(岩波書店)、「ウィルス・プラネット」(飛鳥新社)など多数があります。
生きているとは、どういうことかがわかる私たちの感覚は、まず自分自身の生の自覚から、そして生物と無生物を見分ける、直観的能力から生まれています。生きているとは死んでいないということなのです。人類が死を認識した初めての証拠は、およそ10万年前にありました。彼らは葬儀を始めていたのです。ヒトは、死を単なる物理的な変化とは考えず、社会的な変化、つまり別離とみていました。死者は別の世界に行くと考えたのです。
17世紀後半に、レーウェンフックが顕微鏡を発明すると、ミクロの世界の微小な動物などが続々と発見されました。そこに生命が一時停止され、また蘇生する事例があって、人々は、自分もそのような仮死状態になるかも知れないという不安に襲われました。実際に早まった埋葬の悲劇もありました。脳死の判定が、重大な社会問題となったのです。
しかし、生命の特徴は腦だけではありません。粘菌は腦がないのに、生命の意思決定を、生化学的メカニズムのみで行っています。粘菌は迷路で最短ルートを見つけました。
粘菌は胞子を出し、それが着地するとアメーバ細胞がはい出てきます。染色体は半分ですが単独で生き、ほかの粘菌の細胞に出会うと、接合して染色体を合わせた巨大な細胞になり、あるいは他の粘菌とネットワークをつくったりもするのです。また浮草に付着する「ヒドラ」は、ミジンコなどを捕食する小動物ですが、いくつに切り分けても、断片がそれぞれに再生し、頭と胴と触手を持つ完全な個体になるのです。生命体の不思議でした。
20世紀に入ると、酵素の研究が進み、やがて量子物理学が登場します。遺伝子が「生命の基礎」とされ、染色体との関わりが明らかになってきました。シュレーデインガーは「生命とは何か」を論じ、生命が秩序を保つには、エントロピーの増大に逆らうよう、エネルギーを取り込むことだと説きました。DNAが生命の象徴となり、クリックとワトソンによる二重らせんモデルがノーベル賞を受けます。ここであらためて生命の定義が論じられました。「生命とは、ダーウィン的進化を起こさせる自立した化学的な系である」と。
またウィルスは生物学者の頭痛のタネでした。自立した化学系ではないが、遺伝子をコードするのにDNAでなくRNAを用いて、宿主の細胞の化学的系のなかで存続し、変異を重ねて進化します。しかし現代の分類体系では生物に含めてはいないのです。赤血球も、生命の境界にありました。骨髄の細胞でつくられて、ヘモグロビンを持ちますが、DNAはなく、ミトコンドリアもありません。「生命の定義」は揺れるばかりでした。
「生命の起源」についても様々な議論があり、今や宇宙にまで及んでいます。著者は、各地の専門家を訪ね、多くのエピソードも交えて、生き生きと語っていました。「了」
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2018年2月
カテゴリー
タグ一覧