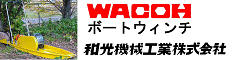岸 由二著、ちくまプリマー新書、2021年7月刊
著者は、1947年東京に生まれ横浜で育ちました。横浜市立大学生物学部卒、東京都立大学大学院で理学博士、慶応大学名誉教授。専門は進化生態学。流域アプローチによる都市再生に取り組み、現在も鶴見川流域で実践活動を続けています。著書に「自然へのまなざし」(紀伊国屋書店)ほか多数、共訳にドーキンズ「利己的遺伝子」(同)などがあります。
豪雨災害の時代が始まっています。大小の河川が氾濫し、その都度大きな被害が出ました。著者は横浜で、都市河川の下流域の水害を何度も体験しています。水害については、行政も一般も最近まで、河川が引き起こすものとみてきました。しかし実際に河川に大量の雨水を注いでいるのは、大地の広がりと凹凸がつくる「流域」という地形でした。流域という基本地形は、水循環のさまざまな過程や機能を介して、多種多様な生物を支える生態系でもあります。流域に降る雨水は、一部は蒸発して大気に戻りますが、多くは植物を濡らして地表を流れ、地面に浸透して地中を移動し、ともに河川に流入して海に至ります。雨水は流域において、集水、流水、保水、増水、遊水、氾濫、排水の各段階で、浸食、運搬、堆積作用を示し、降雨量とそのパターンで大きく変わります。国交省は2020年、「流域治水」の基本方針を打ち出しました。画期的な方針転換で、著者らの提言がここに結実したのです。
著者は地元の鶴見川の流域治水に挑戦しました。東京都町田市の標高160mの多摩丘陵の森が水源で、川崎市の一部を通り、横浜市鶴見区生麦で東京湾に注ぐ1級河川で、本流の流路延長はマラソンとほぼ同じ42,5km、流域面積235km2、流域人口は200万人(現在)に及ぶ、典型的な都市河川です。鶴見川の水害は、江戸時代から記録があり、明治以降も激しい災害を繰り返しました。戦後を見ても1958年の狩野川台風の大水害を筆頭に、82年にかけて5回も起きました。その理由は流域の構造にありました。上流の多摩丘陵の水は、中流で下末吉大地を刻み、支流の恩田川を併せて大蛇行しながら下流の沖積低地を流れます。河口まで13kmは6500年前の縄文時代には浅い海と干潟でした。蛇行部分は流速を落として氾濫を拡大させます。とくに戦後、田園地帯が急速に市街地となった影響は甚大でした。
40年前、この鶴見川に一級河川では全国初の試みとして、「流域治水」が開始されました。流域全体に、保水地域、遊水地域、低地それぞれの機能を強化しました。公園を兼ねた多目的遊水地、下流部の大規模浚渫、支流域の河川整備、下水道の普及、大規模緑地の生物保全などが、降雨パターンに合わせて計画され、国交省、自治体、市民団体の連携で、対応しました。効果は絶大で、気候変動の激しかったこの41年間で、河川氾濫は殆ど発生していません。50年に一度ともいう、300㎜の降雨にも耐えることができるようになったのです。
専門的には、洪水と氾濫は違います。大雨で河川の流れが大きくなるのが洪水で、川の外に溢れ出るのが氾濫です。降雨量が多くとも、安全に洪水として川に流すのが河川の仕事なのです。鶴見川流域には、工業利水、水道利水はほとんどないので、ダムはありません。水系に沿って源流から上流、中流、下流、海まで連続した流域世界には、豊かな生物多様性が展開しています。流域思考こそが、気候変動の危機を生き延びる決め手になるのです。了
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2018年2月
カテゴリー
タグ一覧