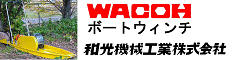著者は、1941年生まれの哲学者です。文芸批評から出発しながらカント、マルクスなどを論じ、多彩な活動を展開しています。著書には、「マルクスの可能性の中心」、「日本近代文学の起源」、「世界史の構造」、「哲学の起源」、内省と遡行」などがあります。
人類学者は、これまでいわゆる未開社会を扱ってきました。そこには共通する原理があるといいます。その原理とは、贈与する義務、受けとったらお返しする義務、つまり互酬的な贈与の関係があったというのです。しかし著者は、この互酬原理は、遊動的な狩猟採集民の段階には存在せず、定住後に形成されたものとみています。遊動したら獲物を備蓄できません。所有する意味もないので、全員に均等分配します。定住後に互酬原理が生まれたのです。
農業、牧畜が始まると、人びとが定住し、生産力が増大して都市が発展し、階級ができて国家が生まれたといいます。しかし、農耕以前に定住は始まっていました。縄文文化は、狩猟採集しながら定住して、簡単な栽培や飼育を行っていました。生産物の蓄積、富や力に格差が生まれて、国家に発展する可能性もありました。ところが定住した狩猟採集民が、それを斥けたのです。定住はしても、遊動民時代の在り方を維持するシステムを創出しました。著者はこれを、農耕と牧畜による「新石器革命」でない、「定住革命」と呼んでいます。
日本で遊動民に注目した思想家は柳田国男でした。彼は、2種類の遊動民を挙げています。まず「山人」は、日本列島に先住した狩猟採集民でしたが、農耕民に追われて山に逃げ込んだ人びとといいます。また「芸能的漂泊民」がいて、定住性とそれに伴う服従性を拒否しますが、定住農民(常民)共同体を交易などで媒介して、一方では国家「王権」ともつながる存在でした。定住民に差別されながら、他方で定住民を支配する影の力を持っていたのです。
著者は、ここで「柳田国男論」に深入りします。その手がかりとしたのは、柳田が戦争末期に、敗戦を予想して日本民族の行く末を探った「先祖の話」でした。柳田の実父、松岡約斎は医者で、中年から平田篤胤派の神官になりました。柳田は、幼少のころから幽冥界や妖怪に関心がありましたが、のちに民間信仰を軽んじた平田神道を強く批判しています。東京帝大で農政学を専攻し、農商務省の官僚となりましたが、大審院判事の柳田直平の養子に迎えられました。彼は柳田家の先祖を訊ねて、祖霊や固有信仰に触れることになったのです。
柳田の農政学は、最初から史学的、民俗学的なものでした。飢饉に対応する農村を、国家に依存しない共同自助へ導いています。その調査旅行で、焼畑と狩猟で暮らす椎葉村を訪れて、衝撃を受けました。富の均分が実現している共同自助の、奇跡の理想郷を見たのです。柳田が山人について論じたのは、この後でした。椎葉村の人びとは「山人」ではなくて「山民」でしたが、山民たちの共同所有の観念は、遊動的生活から引き継いだものでした。
山人は見つからなくとも、思想として存在していたのです。オオカミを尊ぶのも、その一つでした。固有信仰では、神は祖霊たちの力の融合と考えています。先祖の霊は、家の近くに止まり、盆礼などで生者と交流し、時を経たら山に昇り、子孫の家の繁栄を見守るといいます。神の祭りは、小さく静かに真剣に行うようにと述べた「先祖の話」は名著でした。「了」