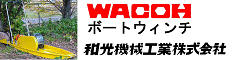生きものと環境の関係を一歩引いたところから考えてみた著作である
ペレ出版、2021年1月刊 著者は、京都大学フィールド科学教育センター准教授です。1972年に徳島の米農家に生まれ、ハーバード大学大学院の進化・個体生物学部を修了しました。(Ph・D)
生態学は理系ですが、その視点は経済学や社会学と共通するところがあります。生態学は、生命現象の背景に注目しますが、それを理解するには、自然現象による環境はもとより、人間の行動による環境もまた劇的な影響を及ぼすことがあるからです。著者は、身の回りのどんなことでも、生物学の視点から仮説を立て、生態学の問題として考えるようになりました。
人間という生物の特徴は、自分で自分の暮らす環境を、好ましい方向に変えてゆく「生態系エンジニア」であることです。しかしそのようにして適応してきた環境が、突然に大きく変化することがあります。今回の新型コロナウィルスの襲来が、まさにその変化でした。
外圧によって変化した暮らしは、もとの姿に戻るでしょうか。高度成長期には合理的だった満員電車通勤、会議や出張などは、リモートや在宅勤務などで、もう戻らないかも知れません。自然界でも、森林火災のように劇的な変化が起きることがあります。安定していたシステムでも、永続する保証はありません。人間社会でも同じこと。万物は流転するのです。
私たち人間は、他者とかかわりながら生きています。その相手は自分の味方か敵か、自分の役に立つのか、それとも自分を搾取するのか。生き物たちの世界も同じです。生物Aからみた生物Bの存在は、「良い」、「悪い」、「どうでもよい」のどれかです。それに、AからみたBと、BからみたAがあるので、その組み合わせは9通りになります。双方に利益があるのは「相利共生」、イソギンチャクとクマノミが良い例です。「片利共生」と「片害共生」は、立場によって利害が反対になること、利害が一方的の場合は「捕食」です。「競争」は同じ立場で限りある資源を奪い合うときに生じます。お互いにどうでもよければ、「無関係」となるでしょう。これらの関係は、ウィルスなどの「寄生」にも当てはまるのです。
この組み合わせに恵まれず不遇な環境にいると、生物は強烈なストレスに襲われます。害虫の多い環境に育ったトマトは、花が咲く前に死んでしまいます。ところがトマトには、食われる前に早く花を咲かせて果実を実らせ、子孫を残すという戦略がありました。ストレスを感じたら性的に早熟すれば、遺伝子を遺すことができるのです。人間も同じでした。安定した社会では晩婚になり、貧困家庭の子どもが早熟になりやすいのは、そのためでしょう。
生態学者の多くは、森歩きを趣味にしています。森林浴だけでなく、「観察」することで、楽しみが倍増するのです。著者のお気に入りは奥入瀬渓谷でした。冷温帯にあって十和田湖からの水量が安定しているので、いろいろの植物がそれぞれの微環境を利用して生きているからです。森のことは行ってみなければわかりません。直観がアイデアを生むのです。
著者は、アメリカの国立公園での一人幕営で、コヨーテの群に囲まれましたが、彼らは賢くて柔軟でした。オオカミが再導入されても、うまく折り合いをつけて生きていました。
進化生物学に「進化心理学」という分野があります。ヒトの身体が自然淘汰で形成されてきたと同じく、私たちの心も進化してゆくのです。著者の旅は、なおも続いています。「了」