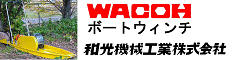せめぎあう土と生き物たち ヤマケイ新書、2016年2月刊
著者は富山県に生まれ、京都大学農学研究科博士課程を出た森林総合研究所研究員で、土壌学、生態学が専門です。先に「土—地球最後のナゾ」を紹介したので、皆さんもお馴染みでしょう。世界を股にかけ、スコップ一つで逞しく土と生き物たちを追ってきました。
すべての陸上生物は、「土」から栄養分をとっています。その「土」が生まれたのは、およそ5憶年前のことでした。まずコケや地衣類が、ついでシダなどの植物が上陸して光合成を始め、その遺体が酸性の腐植となって岩石の風化を早め、粘土と混じって長い年月をかけて土壌が生成されました。生き物たちは、その「土」に居場所や栄養分を求めて、厳しい生存競争を展開してきたのです。「土」は彼らの墓標でもありました。
「土」には、もともと「酸性」という厄介な特性がありました。植物はKイオンやCaイオンなどの陽イオンを多く吸収し、根から水素イオンを放出します。微生物たちも落ち葉を分解して、有機酸や炭酸、硝酸などの酸性物質として放出します。また水の浸透によって岩石からはカルシュウムが溶け出して二酸化炭素を吸収して炭酸カルシュウムとなり、乾燥地ではアルカリ性になりますが、降水量が増加して土を洗い流すとこれもまた酸性に変わってゆきます。さらに酸性雨の働きも加わり、大地は次第に酸性になってゆくのです。
特に日本では酸性土壌が多く、その農業はこの酸性との戦いでもありました。その土壌改良に苦闘した先人の一人に、宮沢賢治がいました。東北地方の酸性の黒ボク土に、石灰肥料を普及させる事業に奔走したのです。「春と修羅」に青いアジサイの詩があります。アジサイの色素は、もともとピンクのアントシアニンですが、日本の酸性土壌では、粘土からアルミニュウムイオンが溶け出して、花(ガク)を鮮やかな青色に染めるのです。
同じ黒ボク土でも、ウクライナのチェルノーゼムなどはカルシュウムが多く含まれて、世界の穀倉となっていますが、日本の場合は降り積もった火山灰で酸性が強く、作物にとっては肥沃ではありません。しかしブナやスギはこの酸性を克服してよく育ちます。そこで樹木に栄養を取らせて肥料とする、焼畑や里山利用農業が営まれてきたのです。
地球の生態系は大きく変化してきました。3億年前、これまで優勢だったシダ類に代わって裸子植物が出現します。鉄酸化物で根を囲って水辺でも通気性を保ち、土壌を酸性化して外生菌根菌で栄養をとりました。リグニンで幹の強度を高めて背を伸ばし、光を存分に受けて地上を制覇しました。恐竜の時代です。1.5憶年前になると、今度は被子植物が出現して、フタバガキが熱帯で大繁栄します。熱帯雨林は貧栄養の森でした。有機物を含む肥沃の表土は薄く、その下は栄養のない酸性の土ばかりです。岩石の風化が早くリンが少ない。フタバガキはこの酸性とリンの不足を、土を介しての外生菌根菌との共生で克服したのです。森は循環します。微生物が食べられなかったリグニンも、白色腐朽菌が引き受けました。シロアリやゴキブリ、ミミズにカブトムシの幼虫などの貢献も多大でした。
本書では、土をめぐる自然現象の緻密さと、ヒトの酸性土壌への適応事例を、古代文明から近代まで縦横に語っています。縄文から続く先人の知恵は興味深いものでした。「了」