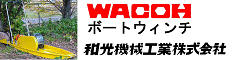ボーイング747のメカニズムを楽しむ
講談社ブルーバックス、昭和55年6月刊 新型コロナウィルスの感染拡大で、図書館がすべてお休みになり、仕方なく書棚の古い本を眺めていたら、本書が目にとまりました。
昨年の秋ころに、ジャンボとエアバスA380が、ともに生産中止になると聞いていたからです。一世を風靡した巨大技術が、終焉を迎えようとしていました。大型機で効率よく世界のハブ空港を結び、中小型機で地方へ飛ぶというビジネスモデルが、高性能中型機で世界の隅々まで直行することで、脆くも崩壊したのです。さらに新型コロナの衝撃は決定的で、巨大航空機の命運は尽きました。今回、はからずもそのジャンボを偲ぶ再読となった本書は、技術史としても貴重なものでした。
1970年代に就航したジャンボは、アメリカ空軍戦略輸送機の開発受注に失敗したことから生まれました。第2次大戦後、世界各地に展開する米軍に、大量の兵員や兵器を即時に供給する戦略に必須な、前代未聞の巨大航空機の計画でしたが、落札したのはロッキード社でした。そこにパンアメリカン航空会社から、超大型旅客機の引き合いがきたのです。
ボーイング747計画が始動したのは、1965年11月のことでした。緊急時に90秒以内に乗客全員が脱出できるために、操縦席だけ2階に上げて、客室は天井の高いワンフロアとし、床下が大容量の貨物室になりました。1号機は重量オーバーとエンジン推力不足に悩みながら、最大離陸重量330トンで、ようやく初飛行ができました。その後も苦労を重ねて747-200Bで、はじめて最大速度1020Km/H、最大燃料193000Kl(約154トン)で、10500Km(米西海岸・東京間)を飛ぶことができたのです。その構造設計は、大きさとの戦いでした。
著者は、ジャンボの出力10万馬力の航空性能を、出力1000馬力のゼロ戦と比較して、ジャンボのほうが身軽であることを示しています。ジャンボの構造も詳細な図解で、設計者の苦労がよく表れていました。その一つが、「ダッチロール」を小さく抑えていること、また室内の与圧でかかる外板への負荷を単純な算数計算で示し、さらに胴体尾部の隔壁の強度が重要だと指摘していました。しつこいほどのフェールセーフ構造とみていたのです。
しかし、本書が出た僅か5年後の1985年8月、あの悪夢のような日航機事故が発生しました。著者の指摘が、そのまま事故の要因となっていたのは、まことに残念なことでした。
ジャンボの構造では、さらにエンジン、主翼とそのフラップ、車輪、ブレーキ、油圧ポンプ、ドアなどに、さまざまな技術がありました。またソフトのメカニズムも革新的なものでした。従来の旅客機では、正・副操縦士に航空士、機関士の4人で運行していたのに、ジャンボでは機長、副操縦士、機関士の3人だけで運行します。航空士の仕事が慣性航法装置(略称INS)に代わったからでした。ジャンボの計器盤は壮大なデザインで、機長の視覚はまさにオーケストラを指揮しているように目まぐるしく動きます。自動運転装置はありますが、最後の頼みは人間パイロットなのです。一つの頂点を極めた技術の物語でした。
巨大システムの開発には確固とした思想が必要です。実現は現実的に、目標は理想的に保つことです。それでもなお市場とニーズの変化を見落としてはなりません。本書は、巻末付録に飛行機地上誘導手信号要領図があります。詳しい図解が満載の、楽しい一書でした。了