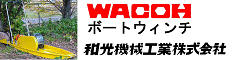役に立つウィルス・かわいいウィルス・創造主のウィルス
さくら舎、2019年1月刊 著者は、名古屋大学大学院出身の医学博士で、現在は東京理科大学理学部教授です。専門は、巨大ウィルス学、分子生物学、細胞進化学などで、2015年に東アジア初の巨大ウィルスを発見しました。「DNA複製の謎に迫る」など、一般向けの多くの著書があります。
ウィルスは、私たちの周りのどこにでもいます。また体内にもごく当たり前のように存在しています。私たちは、ウィルスの海の中を生きているのです。一般にウィルスといえば、すぐインフルエンザとかノロウィルスなどの恐ろしい病原体を思い浮かべますが、病気をもたらすウィルスはごく限られた存在で、ほとんどのウィルスは、ヒトに悪さをしません。
病気を起こさないウィルスは、これまであまり注目されませんでした。ところが最近になって、それがものすごく、たくさんいることがわかってきたのです。 ウィルスは、細胞を持たず、代謝をせず、自力で複製することができません。そのために生命を持たない「物質」とみなされてきました。微生物でもない、やや複雑な構造を持つ「有機物」としてです。
ウィルスの大きさは、細胞よりも1~2桁小さいナノメートルの単位です。可視光線の波長よりも小さいので、電子顕微鏡でなければ見えません。ウィルスは無色透明で、基本形は「カプシド」という殻に包まれた核酸が、幾何学的な正二十面体に結晶化しています。この形が細胞に最もくっつきやすいのです。また細菌にだけ感染するバクテリオファージというウィルスがいますが、正二十面体のカプシドに長い脚(尾?)があって、一見して月着陸船のようです。硬い細胞壁の宿主に取り付いて、頭部にあるDNAを注入する工夫でした。
ウィルスのライフサイクルは、①吸着→②侵入→③脱殻→④合成→⑤成熟→⑥放出 という6ステップです。具体的には、②は細胞に食べられること。③は、核酸の殻からDNAかRNAを細胞内に解き放つこと。④⑤は、細胞に自分の遺伝子の核酸をつくらせて、子ウィルスを組み立てること。⑥は、パンパンに溜まった子ウィルスを一気にまき散らすことで、元の細胞を殺して出てゆくものと、殺さずに出てゆくものがあります。ウィルスは一つの細胞に複数が侵入することもあり、その細胞は「ウィルス工場」として乗っ取られます。ウィルスは、自分の生産設備を持たず、自分の設計図だけを持ち歩く、シンプルで最高の効率を挙げる、究極のミニマリストなのです。しかし、侵入できる宿主にうまく辿りつけるかは、全くの運任せです、極小の世界での水分子の熱運動による偶然に支配されていました。
さて、ウィルスは長い間、病気をもたらす厄介者とされてきましたが、ごく最近になって、「地球生態系になくてはならないプレイヤーであり、恩人である」という評価に変わりつつあります。そのきっかけは、1992年のイギリスでの「巨大ウィルス」の発見でした。そのカプシドは、小型の細菌よりも大きく、しかも翻訳用の遺伝子まで持っていたのです。もとは生物だったのではないか。進化で複雑化するとは限りません。真核生物とウィルスは、遺伝子を交換してきた形跡があります。ヒトゲノムも半数以上がウィルス由来でした。著者は「生物の細胞核は巨大ウィルスの祖先がつくった」という斬新な仮説を立てています。「了」