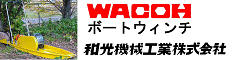アジア史から一望する ちくま新書、2018年7月刊
著者は、アジア史を専攻する京都府立大学文学部教授です。古代から現代までの世界史について、従来のギリシャ・ローマ文明から始まる西欧中心的歴史観を大胆に覆し、ユーラシア全域と海洋世界の変遷を視野に入れた、新たな「世界史の構造」を明快に語っています。
現代のあらゆる学問は、すべて西欧で生まれました。歴史学についても同じで、意識しなくても底流にはキリスト教が影響して、その進歩・発展史観に縛られてきたのです。マルクス史観によって、ようやく「アジア的生産様式」に触れ、西洋以外にも世界があったとはしましたが、その取扱いはあまりにも粗雑なものでした。著者は、その西欧中心史観からの脱却をめざして、あくまでも歴史学の王道にのっとり、アジアの具体的な史実に立脚した、新たな世界史を構築してゆきます。そこで注目したのは、東西交渉史の系譜でした。
古代文明はまずオリエント・インダス・黄河で生まれました。人類がはじめて文字を発明して記録を残し、歴史が辿れるようになったのです。その発祥の地は、いずれも大河の畔で、豊かな水による農耕が起こりますが、周囲はほぼ乾燥地帯で、遊牧民の世界でした。農耕定住民と、移動の活発な遊牧民が近接していたので、双方は接触・交渉せざるをえません。お互いの集団・組織を運営するため、意思疎通・記録の手段としての文字が必要になりました。自分たちの集団だけなら、口伝や習慣だけで済んだはずです。縄文時代がそれでした。
遊牧民は、普段は農耕定住民との交易で日用品を調達していました。しかし、そこにはトラブルがつきものです。軍事力では、遊牧民が日常生活そのままが軍事技術、遠征に転用できて圧倒的に強力ですが、それでは永続的な交易はできません。その仲介で商人が活躍します。この遊牧・農耕・商業が交叉して、古代文明が生まれました。オリエント文明は拡大して、古代ペルシャ帝国が栄え、その西に向かった外延にギリシャ・ローマが生まれました。地中海文明は、オリエントの一部だったのです。また東に向かった文明は、中央アジアを超えて黄河文明に繋がります。ところがそこに地球規模の気候変動、寒冷化が襲いました。
古代文明の遊牧(軍事)、農耕(生産)、商業(交換)のバランスが崩れ、「民族大移動」が起こりました。王朝の興亡がしきりで、生存の危機に人々は宗教に頼ります。中でも7世紀に生まれたイスラームは急速に勢力を伸ばし、ほぼ地中海を制覇しました。一方東ユーラシアのモンゴル草原には、匈奴、突厥などの強力な遊牧国家ができて、東の中原を席捲し、西はトルコ系遊牧民がイスラーム化して躍動しました。やがてチンギス率いるモンゴル帝国が誕生して、東西のユーラシアを統合し、全陸路を抑えます。クビライの代には、遊牧と農耕、移動と定住を有機的につなぐ経済組織を構築しました。すでに商業資本の発想です。
16世紀の大航海時代は、その交易を陸から海へと劇的に転換しました。大西洋航路、インド洋航路の開発で、シルクロードのモンゴルや、地中海のイタリアが凋落してゆきます。世界史の主役が交代しました。覇権は、スペイン、ポルトガルからオランダへと移ります。オランダの興隆の一因には、造船用の森林資源がありました。その地位を奪ったのが新興国の大英帝国でした。原動力は、君民一体の強力な軍事力と、法の支配だったのです。「了」