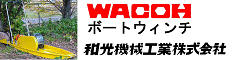周防 柳著、NHK出版新書、2023年3月刊 著者は1964年、東京に生まれた作家です。早稲田大学第一文学部卒、編集者・ライターを経て、「八月の青い蝶で小説すばる新人賞。日本史を扱った小説が多数あります。
古い時代ほど資料が乏しいので、「仮説」を膨らませた小説が盛んです。本書では、それらの小説を通して謎だらけの古代史を眺めることにしました。小説から歴史を探るのは、方向が逆のようですが、その「仮説」は、それなりの思考実験で生まれています。そこに真実が隠れているかも知れません。新鮮な切り口に驚くこともあります。楽しい試みでした。
まず邪馬台国と卑弥呼についての小説を取り上げてみましょう。帚木蓬生の「日御子」では、筑紫の王たちの通訳を務めた「あずみ族」が主人公です。通訳の立場から魏の使節たちを迎えた様子を活写していました。文献学では、魏の使節は伊都国にとどまったとしますが、本書の使節たちは意欲満々、異国の地を隅ずみまで巡ります。倭国からの朝貢に対する単なる返礼でなく、探査が目的の調査団でした。御井(現在の久留米市)の王宮に住む、ヒミコとのやりとりや、道中の描写は見事でした。豊田有恒の「倭の女王・卑弥呼」は、父方が騎馬民族、母は漢の曹操の娘という奇抜な設定です。ある日、叔父の一派に襲われて、弟と二人だけが生き残りました。復仇して筑後川一帯を治め、自由奔放に生きたとしています。
畿内説では、内田康夫のミステリー「箸墓の幻想」があります。波乱万丈。老考古学者の執念に浅見光彦が挑みます。宮内庁が頑なに秘す何かに、小説の可能性がありました。
邦光史郎の「黄昏の女王卑弥呼」では、伽耶から渡来した「木の花一族」が、衰退した邪馬台国に見切りをつけ、瀬戸内海を苦労して渡り、大和に入って纏向に三輪王朝を樹立します。崇神天皇となりました。国譲りでは、ガンダムの安彦良和の「ナムジ・大国主」と「神武」が出色です。梅原猛の戯曲「オオクニヌシ」でも、先住者の出雲に怨念が残りました。
「三輪王朝」は、4世紀末に終わります。黒岩重吾の「女龍王・神功皇后」では、彼女の生い立ちに迫りました。しかし記紀にある夫仲哀や応神の生まれは、いかにも不自然です。内乱に乗じて、伽耶から応神たちが大挙して渡来し、「河内王朝」をつくったのでしょう。「倭の五王」の時代が始まりました。池澤夏樹の「ワカタケル」は、雄略を取り巻く神話とロマンを語ります。雄略は大悪王とも呼ばれ、ライバルを次々に殺しました。眉輪王の悲劇を、1935年に野溝七生子が「眉輪」で、まるでハムレットのように描いていました。
河内王朝は武烈で絶え、応神の遠い子孫の継体が登場します。皇統を婿入りで繋ぎました。欽明になると蘇我氏が台頭します。この時代は三田雅広の「碧玉の女帝・推古天皇」が全体像を捉えています。宝皇女(後の皇極)で終わりますが、黒岩重吾の「聖徳太子―日と影の王子」も全四巻の大作です。藤ノ木陵の「天駆ける皇子」は、穴穂部王子が主人公でした。皇位継承争いに敗れますが、藤ノ木古墳で注目されました。飛鳥時代は後半に大きな波乱がありました。「乙巳の変」、「白村江」、「壬申の乱」と続きます。小説では井上靖の「額田女王」がありますが、井沢元彦の「日本史の反逆者―私説・壬申の乱」が大胆です。著者も「蘇我の娘の古事記」で、漢皇子が入鹿としました。発想の面白さを堪能した一書でした。「了」
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2018年2月
カテゴリー
タグ一覧