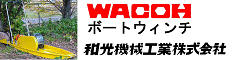田上孝一著、集英社新書、2021年3月刊
著者は、1967年東京生まれ、法政大学文学部哲学科卒、立正大学大学院文学研究科で哲学を専攻した博士(文学)です。専門は哲学・倫理学。現在は、社会主義理論学会事務局長で、「実践の環境倫理学」(時潮社)、「本当にわかる倫理学」(日本実業出版社)、「環境と動物の倫理」(本の泉社)、「マルクス哲学入門」(社会評論社)など多くの著書があります。
世間で動物の本といえば、かわいい写真集とか、マンガや絵本で、心温まるものが一般的ですが、本書は違いました。本書のテーマは、人間と動物とのかかわり方の是非を問う、「動物倫理学」の入門書です。人間に権利があるなら、動物にも権利があるはずでしょう。
倫理学は哲学の一部門です。哲学とは、物事を根本的に深く考える試みです。物事は客観的に存在していますが、倫理学ではその物事を評価して、「善し悪し」を論じます。ある規範があって、為すべきことを行うのです。「法」とよく似ていますが、強制されているものではありません。内面的な道徳的行為で、その規範は時代とともに変わってきました。
人類は、その発生当初から動物と深い関わりを持ってきましたが、西欧ではキリスト教に由来する人間中心主義により、動物は人間と違うという、伝統的動物観が広く根付いていました。動物には意識がない。心がないから苦痛は感じない。哲学者のカントやデカルトでさえも、そう考えていました。動物はモノであるという動物機械論が主流になっていました。
しかし今日、動物関連科学が飛躍的に発展しました。ダーウィンを始めとして、動物と人間は本質的に連続していることが、分子生物学的レベルにまで分かってきたのです。伝統的動物観はもはや通じません。これまでもわずかながら、動物擁護を訴えていた先駆者もいました。その一人がルイス・ゴンベルツ(1783頃~1861)です。徹底して肉食を避け、卵・牛乳まで食べませんでした。ウマなどの利用や、毛皮などにも反対しました。ウマに代わる移動手段として、自転車を発明したといいますから驚きです。もちろんこれは例外でした。
学問としての動物倫理学は、ピーター・シンガー(1946~ )に始まります。著書「動物の解法」は、大きな反響を呼びました。食肉を生産する工場の実態をつぶさに伝えたのです。貴族たちの「キツネ狩り」も取り上げられました。とくに急増した牛の飼育で、環境問題にも発展しています。動物実験は、医学の発展のための必要悪でした。医学は、法的に動物実験を義務付けしています。AIが進歩すれば代替えできるのか、倫理が問われています。
では野外動物ではどうか。娯楽・スポーツとしての狩猟は論外で、人間の都合で「害獣」として駆除することや、狩猟民の生活手段としても、倫理的には擁護できないのです。
動物園や水族館は、野生動物を本来の生息域から切り離し、狭い場所に囲んで苦痛を与えています。飼い慣らされた動物は楽でしょうが、それでは人が来ません。欧米では、動物園廃止論が、学説として有力で、運営側に厳しい注文をつけています。ペットについても、コンパニオン動物としての認識が問われています。生体の売買、所有、増えすぎた場合の個体調整・処理など、やはり動物の権利を尊重する、動物倫理学の対象になっているのです。
本書は、倫理学の立場からの問題提起ですが、様々な議論を巻き起こしそうです。「了」
-
最近の投稿
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2018年2月
カテゴリー
タグ一覧