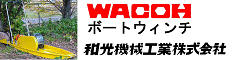合成生物学が生み出しつつあるもの 講談社ブルーバックス2019年8月刊
著者は、米メリーランド大学で海洋・河口部環境科学を専攻し、科学雑誌「ニュートン」編集20年の後、作家となり、生命の起源や宇宙生物学に関する、多くの著作があります。
本書は、生命の起源に興味を持つ「合成生物学者」たちが、人工的に「細胞を創る」研究に取り組んでいる、最前線の動きを生き生きと伝えています。そこには「生命とは何か」という問題を、生命倫理を踏まえながら、哲学や芸術までも含んだ柔らかな視点がありました。
生命の起源に関する研究は、ダーウィン以来、幾多の変遷を経て、一旦は深海の熱水噴出域で生まれた説に落ち着きましたが、近年はまた陸上の温泉や潮だまり説も再浮上しています。横浜国大の小林さんは、前者の立場で、人体の元素の組成が地殻より海水に似ていること、化学反応の条件も揃い、紫外線の影響もなく、温度環境も多彩で、「がらくた」のような多様な物質が生まれて、拡散も容易だったとします。東京薬科大学の山岸さんは後者で、生物の細胞にはNaイオンより、Kイオンが多い、これは陸上の温泉と同じで、海水とは逆だ。有機物が重合しやすい。核酸に必要なリンが多く、RNAが生まれる可能性がある。「RNAからが生物」とみるからです。しかし両者とも有機物の材料は宇宙起源だと一致しています。東北大学の古川さんは、隕石衝突でアミノ酸や核酸塩基ができたことを、火薬銃で衝撃実験を重ねて、その可能性を示しました。隕石は、もともとアミノ酸も核酸塩基も含んでいたので、合わせれば材料が揃うのです。40憶年前には大量な隕石が地球に降り注いでいました。
そのように太古の地球を想定した模擬環境を作って、実際にアミノ酸のような生命の部品ができる様子を観察し、解析してゆく研究が、ここ数十年にわたって続いていました。
一方、工学的手法で生命の起源に迫る「合成生物学者」たちがいました。東北大学の野村さんと海洋研究開発機構の車さんは、キッチンで簡単に人口細胞をつくるレシピを開発しました。人気料理レシピ投稿サイト「クックパッド」に掲載されて話題になりましたが、実際に細胞膜を備えた人工細胞ができたのです。「べシクル」と名付けたこの細胞にDNAを入れてやると、本物そっくりの「細胞もどき」になりました。ただ分裂や増殖まではできません。ここに東京大学が開発した人工セントラルドグマのキットを組み込むと、エネルギー源のATP合成酵素も入っているので、ペンクルの中にたんぱく質ができました。「働く」人工細胞の誕生です。外から栄養を取り込めないのに、数日間稼働しました。あとは「自己複製」だけです。東京大学の豊田さんは、単なる油の粒でアメーバのように変形しながら動きまわり、さらには増殖する、まるで生きている線虫のような油滴をつくりました。東工大の藤島さんは、核酸とたんぱく質が「共進化」した可能性があるとみて、それぞれを組み合わせて、試験管のなかでごく初期の生命「生命0,1」の翻訳系の再現を目指しています。
細胞の「死」から生命を考える人たちもいました。東京大学の田畑さんは、死んだ大腸菌を蘇らせる実験をしています。フランケンシュタインならぬ死体からの「生命の創」。そこでまた生命とは何かが問われることになりました。茨城県の山中に「人工生命の塚」をつくった研究者もいます。生命の刻むリズムは、アートの源泉にもなってゆきました。「了」